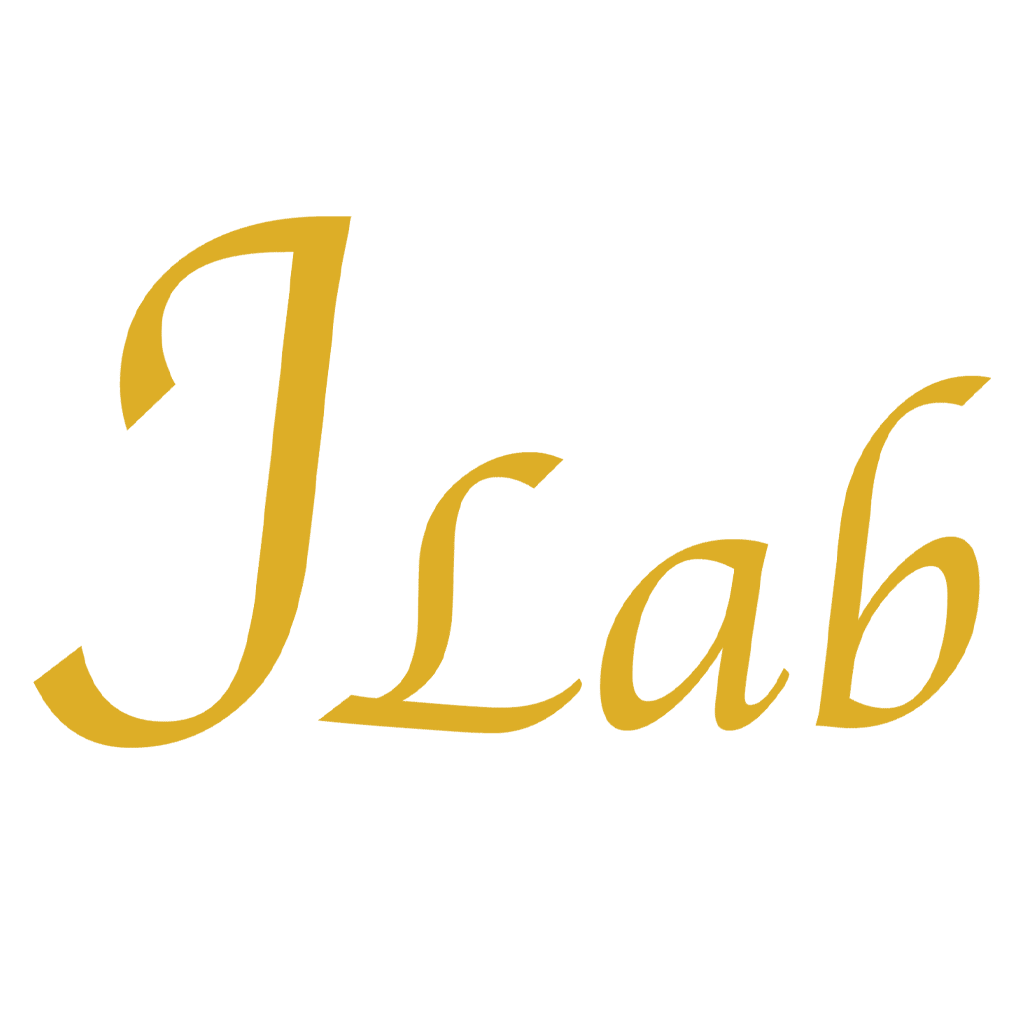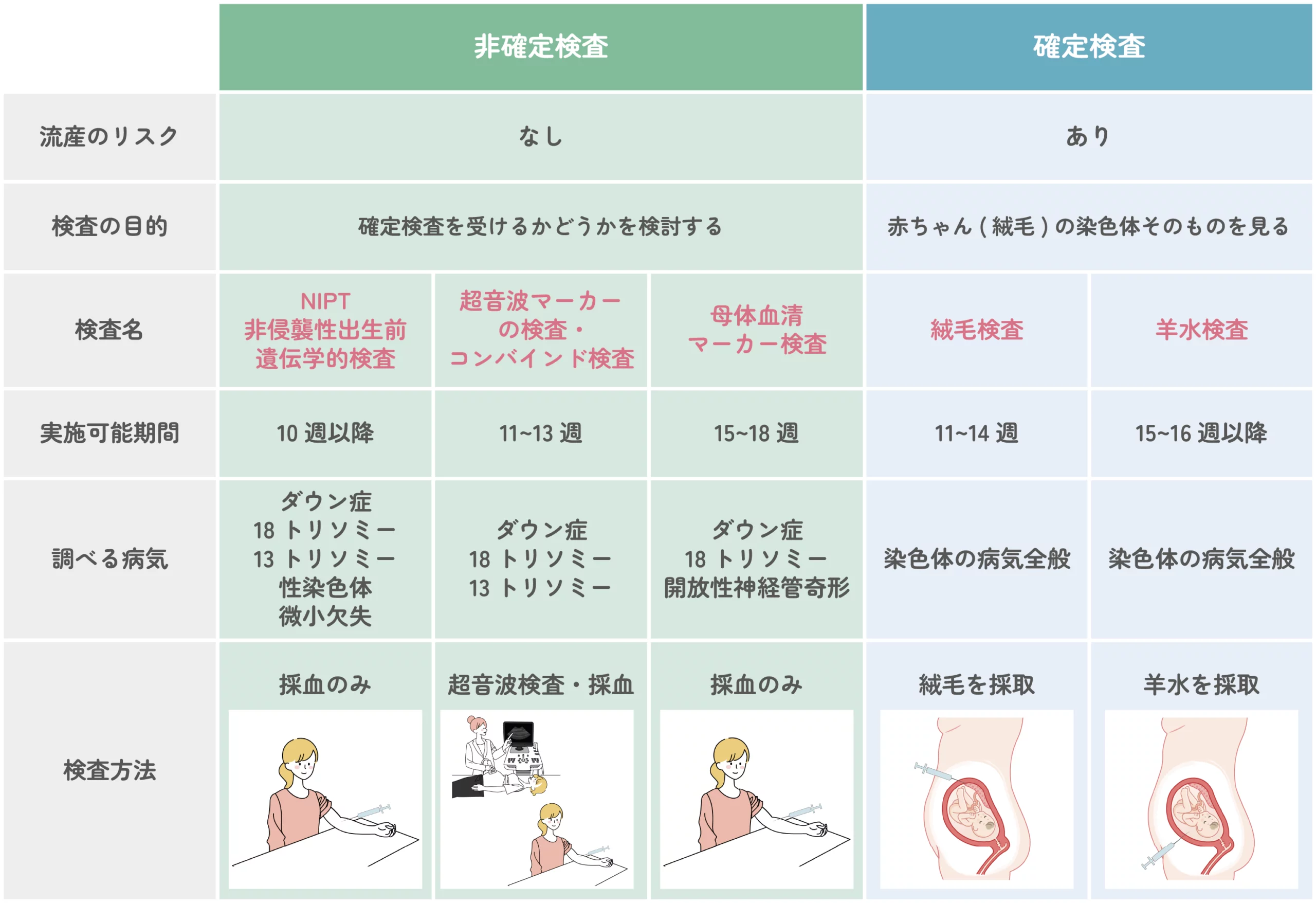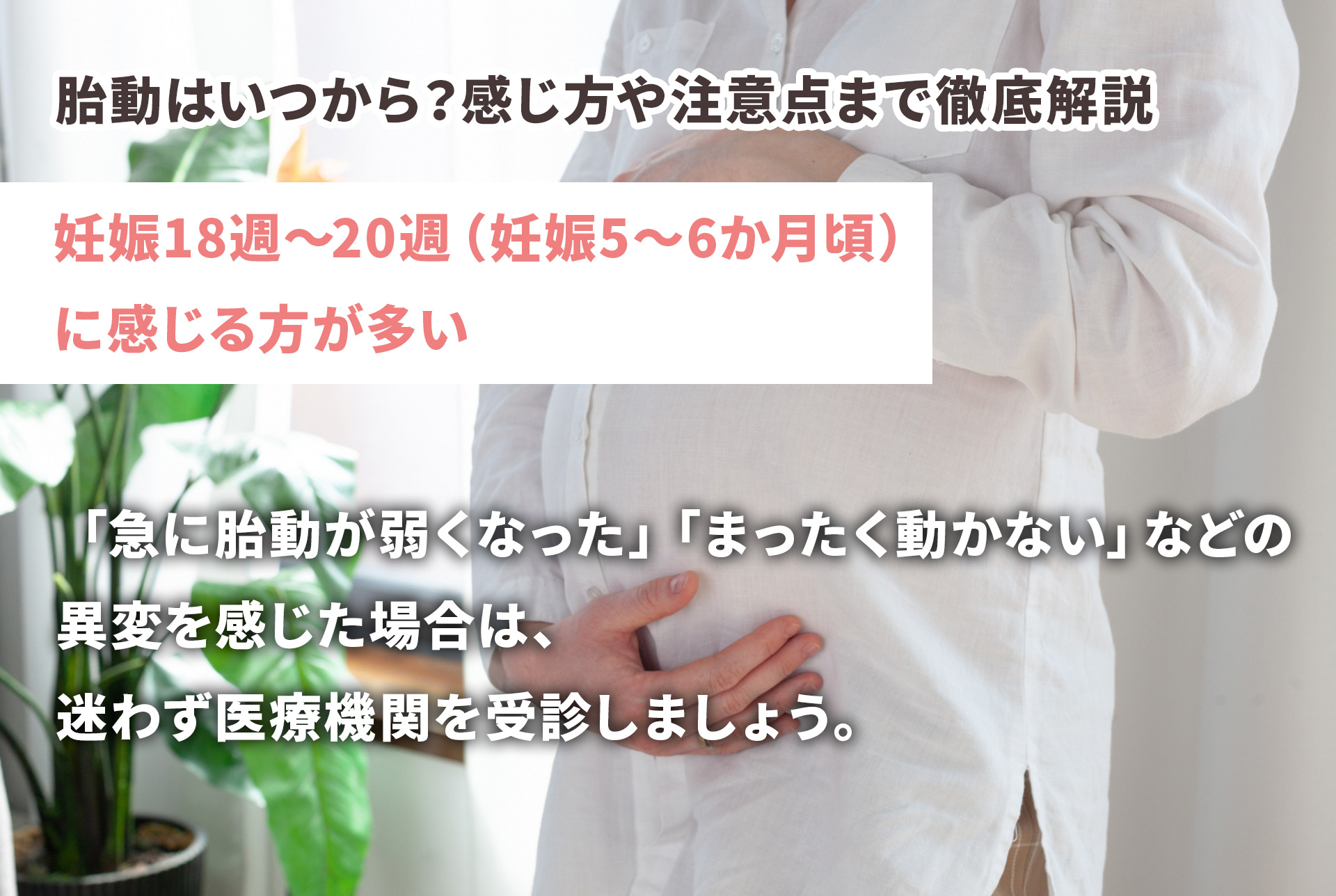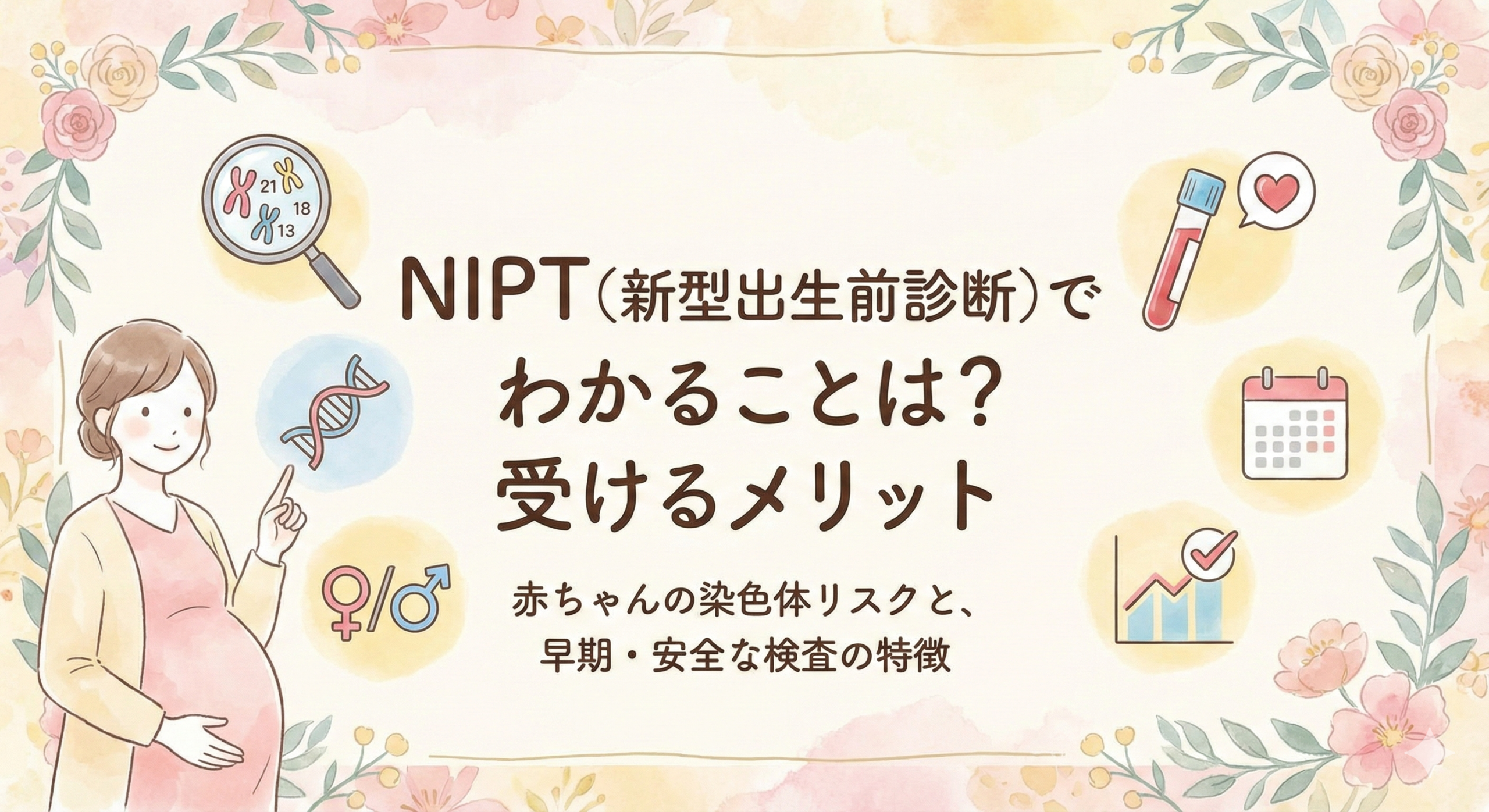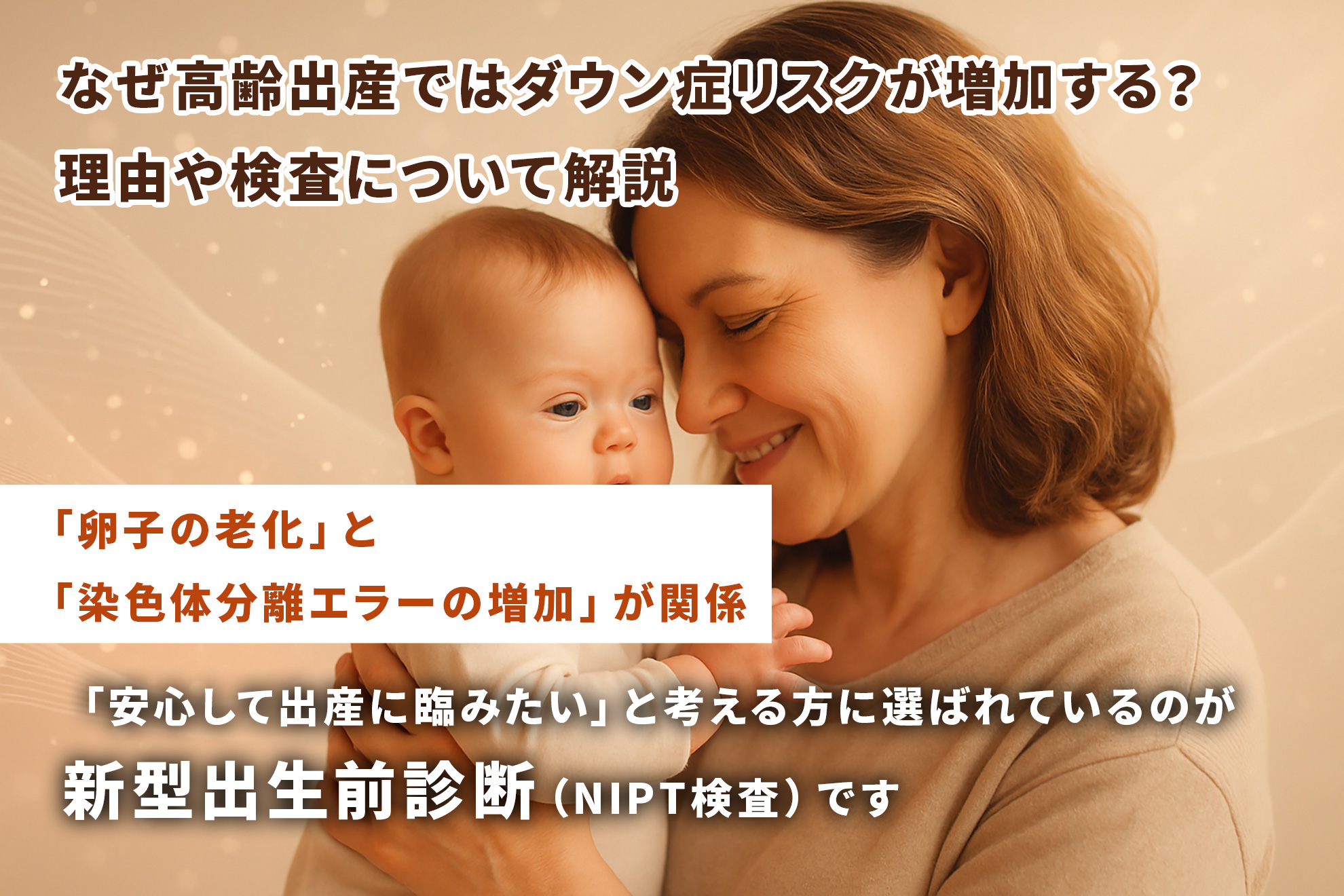切迫流産とは|流産との違い・主な症状・原因・予防と過ごし方まで解説
切迫流産とは|流産との違い・主な症状・原因・予防と過ごし方まで解説
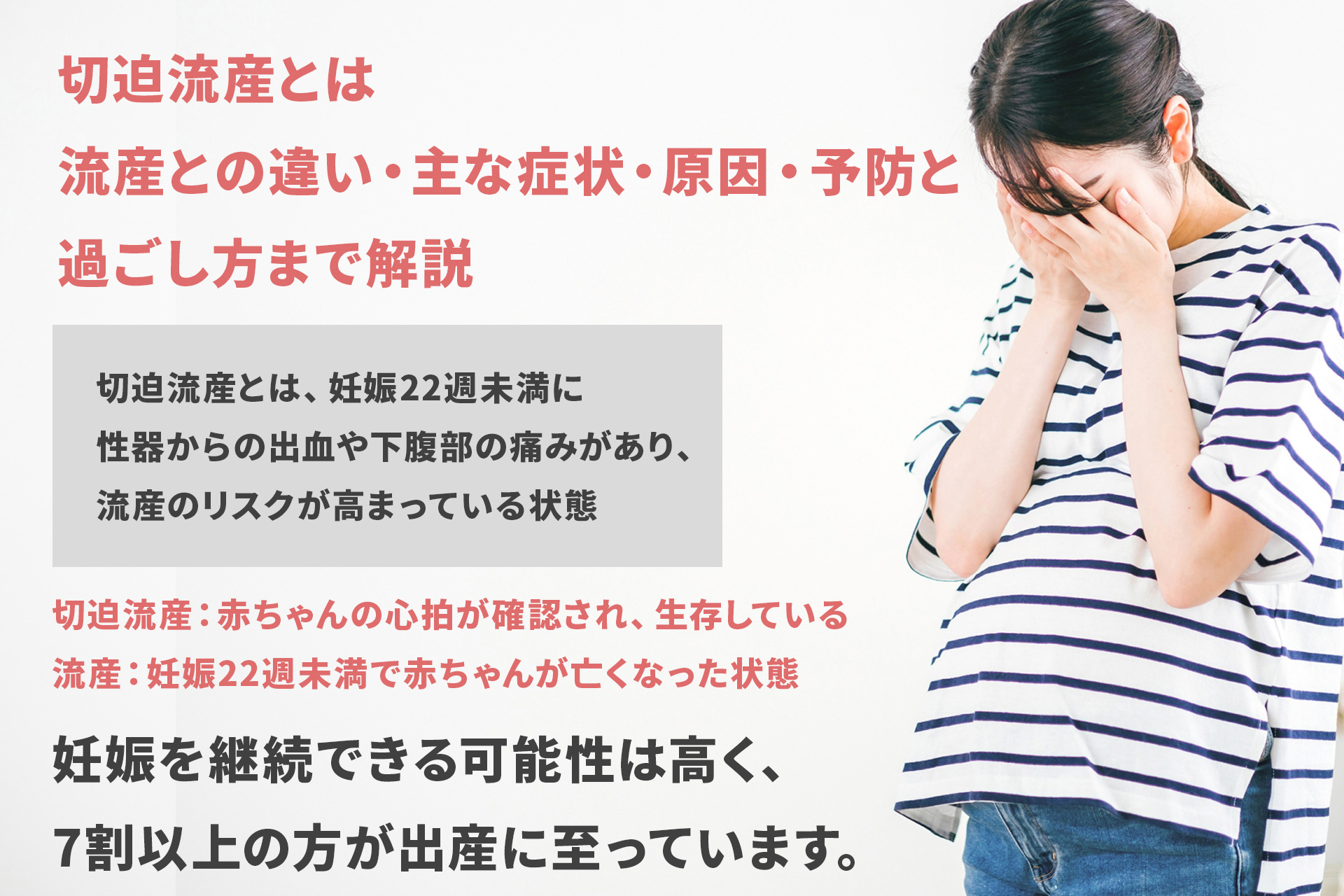
妊娠が判明した喜びの直後、「切迫流産」と診断され、不安に包まれる方は少なくありません。「もしかしてこのまま流産してしまうのでは?」と、心配になるのも当然のことです。
しかし、切迫流産は適切な対応と理解によって、多くの方が無事に出産を迎えています。本記事では、切迫流産の正しい知識とともに、症状の見極め方や予防のためにできることを詳しく解説します。
Contents
切迫流産とは
切迫流産とは、妊娠22週未満に性器からの出血や下腹部の痛みがあり、流産のリスクが高まっている状態のことを指します。
ただし、「切迫」とつく通り、必ずしも流産するというわけではありません。実際、切迫流産と診断された妊婦さんの約7割が、その後無事に出産しています。
切迫流産の程度は人それぞれで、安静にしていれば問題ないケースから、入院管理が必要なケースまで様々です。子宮頸管が閉じていて赤ちゃんの心拍が確認できている場合は、妊娠の継続が可能とされます。
切迫流産と流産の違い
「切迫流産」と「流産」は混同されがちですが、決定的な違いは“赤ちゃんが生きているかどうか”にあります。
切迫流産:赤ちゃんの心拍が確認され、生存している
流産:妊娠22週未満で赤ちゃんが亡くなった状態
流産のうち8割以上は妊娠12週までの初期に起こり、胎児側の染色体異常などが主な原因とされています。ほとんどは防ぎようのない自然な現象で、ママの行動が直接の原因になることは稀です。
切迫流産の主な原因
切迫流産の原因はひとつではなく、複数の要因が重なることもあります。代表的な原因には以下のようなものがあります。
絨毛膜下血腫
妊娠初期~中期にかけて見られる出血の一因。胎嚢(たいのう)周囲に血液がたまる状態を指します。軽度であれば自然に吸収されることもあります。
子宮の異常
子宮筋腫や子宮奇形、内膜症などの器質的な異常がある場合、妊娠の維持が困難になることがあります。
感染症
風疹やクラミジアなど、妊娠中に感染すると子宮内環境に悪影響を与えるウイルスや細菌の存在も原因の一つです。
胎児の染色体異常
特に妊娠初期の流産の多くは、偶発的な染色体異常によるもので、防ぐことはほぼ不可能です。
切迫流産の症状
切迫流産の代表的な症状は、以下の2つです。
- 性器からの出血(鮮血または茶色のおりもの)
- 下腹部の痛み(生理痛のような鈍痛や張り)
これらの症状がすべて流産につながるわけではなく、妊婦さんの約3~5人に1人は妊娠初期に出血を経験するといわれています。
また、ホルモンバランスの変化や胎盤の形成過程に伴って自然に起こる出血もあるため、過度な心配は不要です。ただし、以下のような場合はすぐに医師へ相談しましょう。
- 鮮血が大量に出る
- 痛みが強く、長時間続く
- 出血とともに血の塊が出た
切迫流産を予防するためにできること
妊娠初期の流産の多くは胎児側の理由で避けられないものですが、お母さん側でできる予防策も存在します。
感染症を避ける
風疹やトキソプラズマなどの感染症は、妊娠初期の赤ちゃんに深刻な影響を与える可能性があります。手洗いやマスク着用、人混みの回避など、基本的な感染症対策を徹底しましょう。
妊娠前の検査
将来的な妊娠を考えている方は、子宮の状態を事前にチェックしておくことも重要です。子宮奇形や筋腫、内膜症などは、妊娠継続の妨げとなることがあります。
ストレスをためない
過度な不安や精神的ストレスはホルモンバランスを乱し、体調に影響する場合があります。ゆったりとした気持ちで妊娠生活を送ることが、赤ちゃんにもプラスになります。
切迫流産と診断された場合の治療と過ごし方
切迫流産と診断された場合、「今すぐにどうすればいいのか」「日常生活は続けられるのか」など、さまざまな不安が頭をよぎることでしょう。 ここでは、治療の基本となる考え方や、自宅での過ごし方のポイントについて紹介します。
治療の基本は「安静」
切迫流産と診断された際、多くの場合は自宅での安静が中心となります。必ずしも一日中ベッドに横になる必要はなく、重いものを持たない、無理をしない、こまめに休むなど、身体への負担を減らすことが大切です。
妊娠12週以降の場合には、医師の判断で子宮収縮抑制薬などが処方されることもあります。
医師との連携が大切
症状の程度や妊娠経過には個人差があるため、「どの程度安静にすればよいか」「日常生活で気をつけるべきこと」など、気になる点は医師に確認しておきましょう。
まとめ:切迫流産は正しい知識と落ち着いた対応で乗り越えられる
切迫流産は誰にでも起こり得る可能性がある状態であり、決して珍しいことではありません。しかし、赤ちゃんの心拍が確認できている限り、妊娠を継続できる可能性は高く、7割以上の方が出産に至っています。
大切なのは、不安に振り回されず、正しい情報と医師との連携で冷静に対応することです。そして、ストレスを避けながら赤ちゃんの成長を見守っていきましょう。
Jラボについて
衛生検査所
J-VPD東京ラボラトリー
いまの時代、お客様が検査会社を選ぶことができるのです。
そして、検査会社からクリニックの紹介も行うことができます。
J-VPD東京ラボラトリーの精度管理は厚生労働省と東京都が行っている衛生検査所精度管理調査に参加し、毎年最高評価をいただいております。
J-VPD東京ラボラトリーにはDNAシーケンス解析専門医博、染色体解析専門スタッフ、遺伝子検査専門スタッフなど他にも専門スタッフが在籍し長年の経験、知識をもった熱練スタッフが検査・解析を行います。
- ライセンス情報
-
「東京都登録衛生検査所 認可」を取得
(5新保衛医第294号)
- 所在地
- 〒160-0005
東京都新宿区愛住町23-14
ベルックス新宿ビル6階
- アクセス