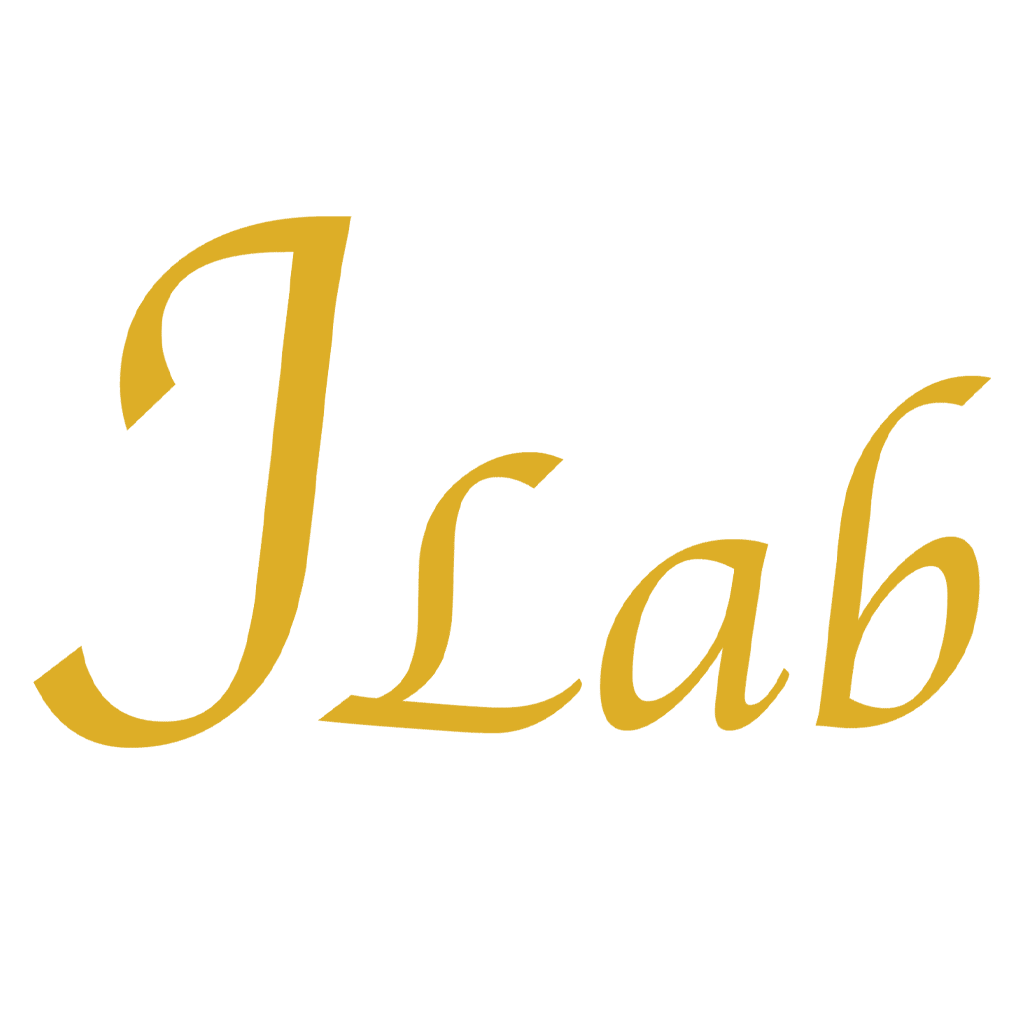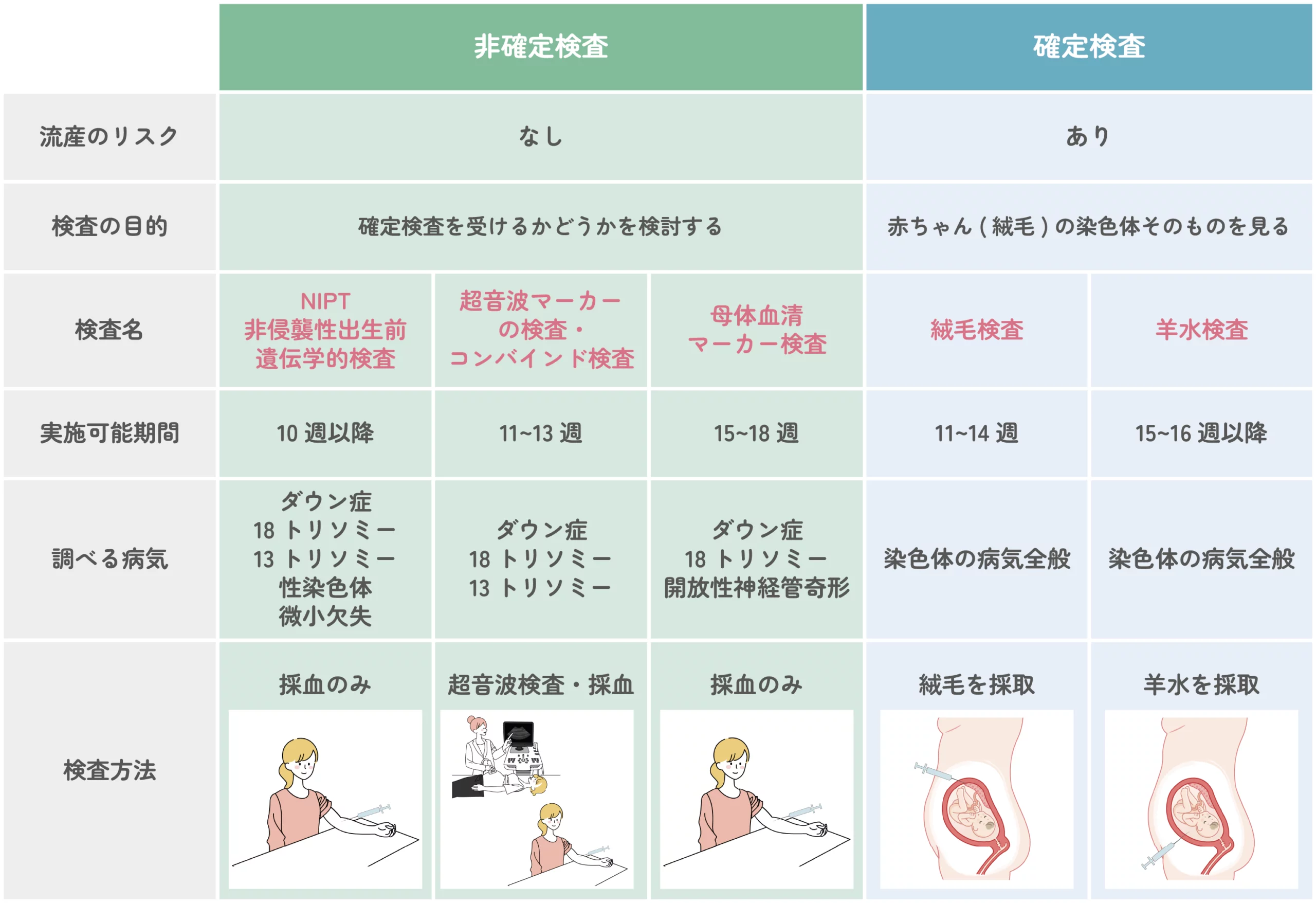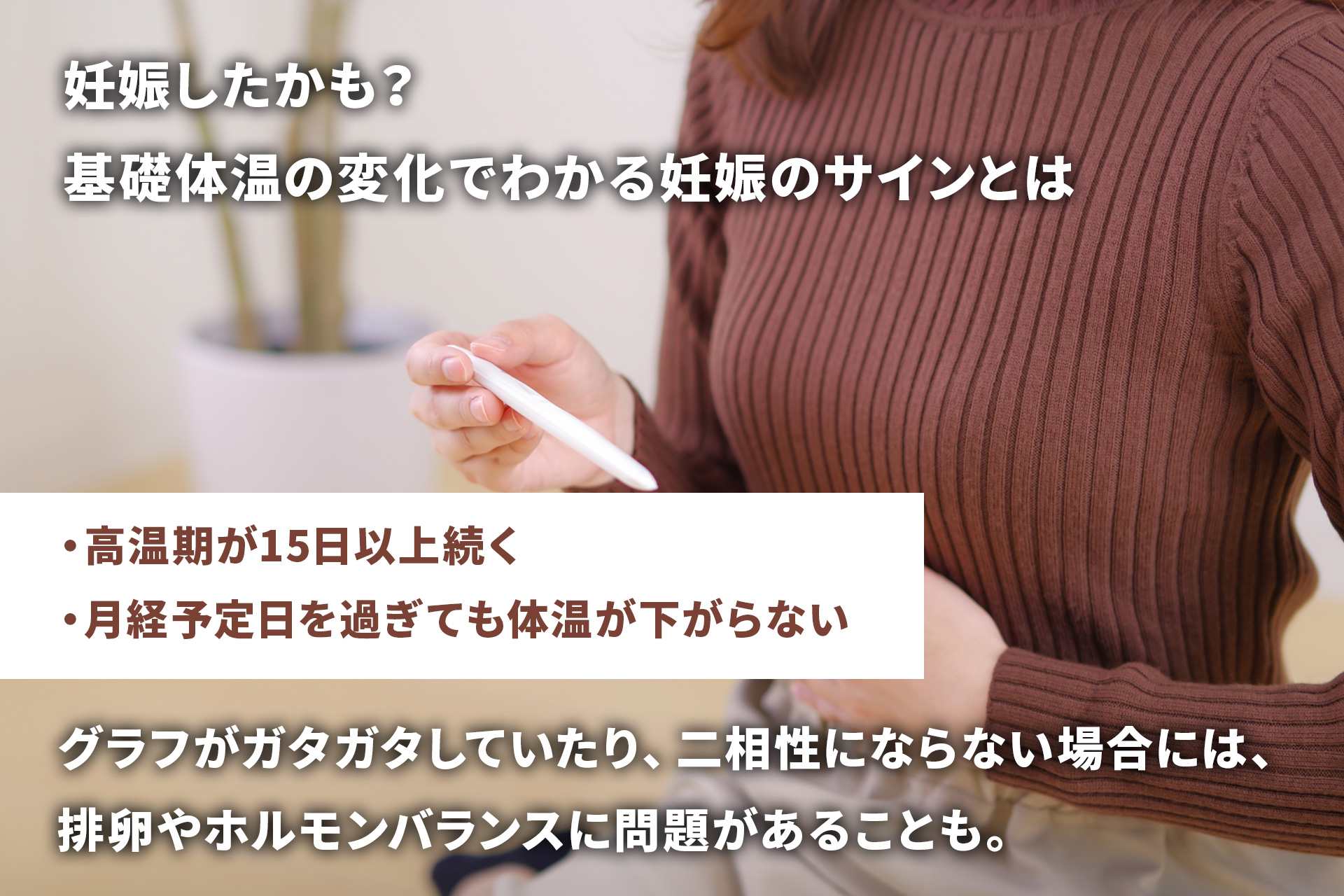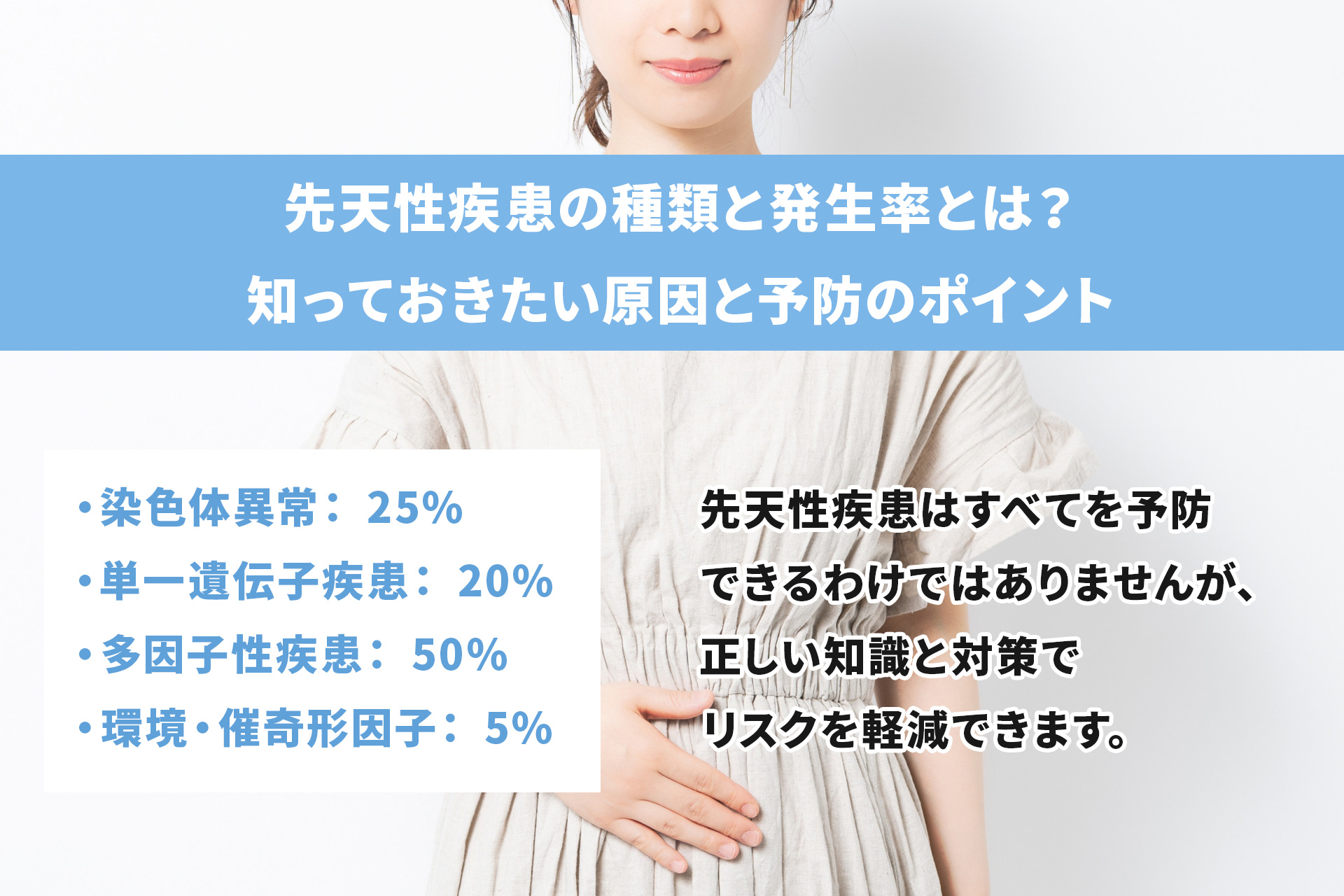帝王切開とは?行われる理由・手術の流れ・費用・傷跡ケアまで解説
帝王切開とは?行われる理由・手術の流れ・費用・傷跡ケアまで解説
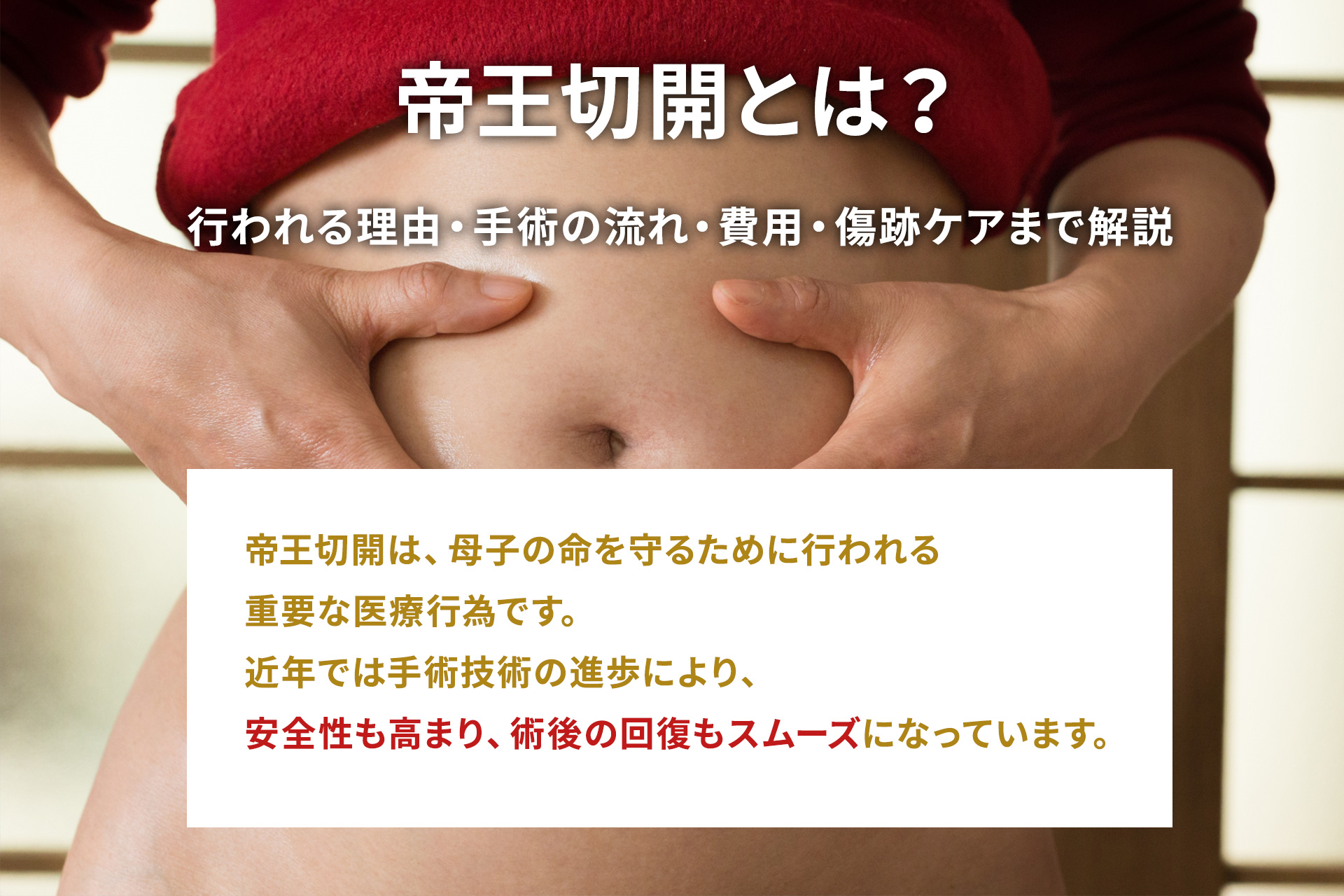
出産の方法にはさまざまな形がありますが、その中でも「帝王切開」は母子の安全を守るために行われる大切な医療手段の一つです。近年では高齢出産や多胎妊娠の増加により、帝王切開で出産する人の割合も年々高まっています。
本記事では、帝王切開が選ばれる理由や手術の流れ、かかる費用、術後の傷跡ケアまでをわかりやすく解説します。
Contents
帝王切開とは
帝王切開は、母体の腹部と子宮を外科的に開き、赤ちゃんを取り出す出産方法です。かつては「最終手段」と考えられていましたが、近年では医療技術の進歩により安全性が高まり、出産の選択肢として一般的になっています。
厚生労働省の統計によると、現在ではおよそ5人に1人の妊婦が帝王切開で出産しており、その割合は年々上昇しています。背景には、高齢出産の増加や多胎妊娠、不妊治療の発展などが関係しています。医師が母体と胎児の安全を最優先に判断した結果、帝王切開が選択されるケースが増えているのです。
どんなときに帝王切開が選ばれるのか
帝王切開が行われるケースは下記2つに分類されます。
予定して行うケース
予定帝王切開は、出産前から日程を決めて実施する方法です。たとえば、胎児が逆子のままである場合や、前置胎盤・多胎妊娠のように経腟分娩が困難と判断される場合に選ばれます。また、過去に帝王切開を行った経験がある人や、子宮筋腫の手術歴がある場合も再手術が推奨されます。
このほか、心臓や腎臓などの持病があり、分娩による身体への負担が危険とされる場合にも、医師の判断で予定帝王切開が行われます。
緊急で実施されるケース
緊急帝王切開は、分娩の最中に予期せぬトラブルが発生したときに行われます。たとえば、胎児の心拍が急激に低下したり、臍帯(へその緒)が圧迫されたりするなど、母子の生命に関わる状況が確認された場合です。
また、常位胎盤早期剥離や大量出血、妊娠高血圧症候群の悪化など、母体の状態が急変したときにも、緊急帝王切開によって安全を確保します。
帝王切開の手術の流れ
帝王切開の流れは下記のとおりです。
手術前の準備
予定手術の場合、前日に入院し、医師や助産師から手術内容の説明を受けます。食事制限や体調管理を行い、同意書の提出を経て準備を整えます。
手術当日から出産まで
手術当日は絶食し、点滴や導尿などの処置を受けます。麻酔は腰椎麻酔や硬膜外麻酔が一般的で、手術時間はおよそ1時間前後です。 腹部と子宮を切開し、赤ちゃんを娩出したあと、出血を止めながら縫合を行います。局所麻酔であれば、赤ちゃんの産声を聞くことができることも多いです。
手術後の経過
手術直後は痛みが強く、鎮痛剤でコントロールします。翌日から軽い歩行を始めると、回復が早まる傾向があります。授乳や食事は体調を見ながら段階的に再開し、入院期間はおよそ1週間が目安です。
帝王切開の切開方法と傷の回復
帝王切開の切開方法と傷の回復について詳しく見ていきましょう。
縦切開と横切開の違い
帝王切開には「縦切開」と「横切開」があります。 縦切開はおへそから下へまっすぐ切る方法で、緊急手術で採用されることが多いです。視野が広く、短時間で赤ちゃんを取り出せるため、迅速な処置が可能です。
一方、横切開は下腹部を横に切る方法で、予定手術によく用いられます。傷が下着で隠れやすく、術後の見た目が比較的きれいに仕上がります。
傷跡のケアと回復の目安
術後3日ほどは痛みが強いものの、1週間ほどで赤みが落ち着きます。傷跡は半年から1年をかけて白くなり、目立たなくなっていくのが一般的です。 ただし、体質や炎症の影響で「ケロイド」や「肥厚性瘢痕」と呼ばれる盛り上がりが残る場合もあります。
清潔を保ちつつ、医師の指導のもとでテープ固定や保湿ケアを行うことで、回復を早めることができます。
帝王切開にかかる費用と補助制度
帝王切開は健康保険の適用対象です。手術費用の自己負担額はおよそ6〜7万円程度で、これに入院費や処置料を加えると、全体で10〜20万円ほどが一般的な目安となります。
出産育児一時金として、子ども1人につき50万円が支給されます。さらに、医療費が高額になった場合には「高額療養費制度」を利用することで、自己負担の上限を超えた分が払い戻されます。
加えて、確定申告時に「医療費控除」を活用すれば、支払った税金の一部が還付される場合もあります。自治体や加入している健康保険組合によって補助内容が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
帝王切開のメリットとリスク
帝王切開は、母体や胎児の状態を安全に管理しながら出産できる点が大きな利点です。陣痛の痛みを回避でき、出産日を計画的に決められるため、家族のスケジュール調整もしやすくなります。
一方で、帝王切開は開腹手術であるため、出血や感染、癒着などのリスクを伴います。また、術後の回復期間が長く、次回以降の妊娠で子宮破裂や癒着性腸閉塞のリスクが高まる可能性もあります。
そのため、医師の説明をしっかり受け、手術への不安や疑問点を解消しておくことが大切です。
二人目以降の出産はどうなる?
1回目の帝王切開が横切開で、子宮の状態が良好な場合は、経腟分娩(VBAC)が可能なケースもあります。 ただし、子宮破裂などのリスクを伴うため、医師による慎重な判断が必要です。
2回以上帝王切開を経験している場合や、子宮の薄さが確認された場合には、再度帝王切開が選ばれることが多くなります。
まとめ
帝王切開は、母子の命を守るために行われる重要な医療行為です。近年では手術技術の進歩により、安全性も高まり、術後の回復もスムーズになっています。
不安を感じることも多いかもしれませんが、帝王切開は決して特別な出産ではありません。大切なのは「どんな方法で産むか」ではなく、「どう育てていくか」です。医師と相談しながら、安心して出産を迎えましょう。
Jラボについて
衛生検査所
J-VPD東京ラボラトリー
いまの時代、お客様が検査会社を選ぶことができるのです。
そして、検査会社からクリニックの紹介も行うことができます。
J-VPD東京ラボラトリーの精度管理は厚生労働省と東京都が行っている衛生検査所精度管理調査に参加し、毎年最高評価をいただいております。
J-VPD東京ラボラトリーにはDNAシーケンス解析専門医博、染色体解析専門スタッフ、遺伝子検査専門スタッフなど他にも専門スタッフが在籍し長年の経験、知識をもった熱練スタッフが検査・解析を行います。
- ライセンス情報
-
「東京都登録衛生検査所 認可」を取得
(5新保衛医第294号)
- 所在地
- 〒160-0005
東京都新宿区愛住町23-14
ベルックス新宿ビル6階
- アクセス